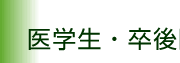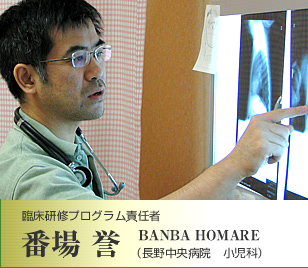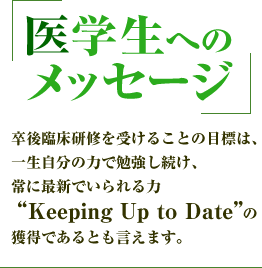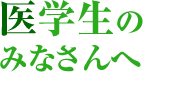
私は1990年に信州大学を卒業し、一般病院での研修を志望して長野中央病院で卒後臨床研修を修了したあと、いくつかの病院での研修を経て、現在、長野中央病院の卒後臨床研修の責任者をしています。
卒後の臨床研修をどこで受けようかと悩んでいる方も、まだたくさんいらっしゃるかと思います。自分自身が臨床研修を受けた経験や、これまで多くの研修医教育に関わった経験から、私なりにみなさんへメッセージを送らせて頂きます。
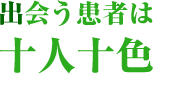

医師としての責任を果たせるようになるためには、典型的な病気をみることよりも色々な困難のある患者に出会い、様々な症状に対応し、たくさんの疾患を鑑別する経験を積むほうが、より勉強になります。また受診(あるいは救急)から入院・退院・在宅治療まで一連の経過をまるごと受け持つ経験こそ研修医時代には貴重な体験になると思います。
1、様々な疾患の鑑別診断を経験すること
(≒疾患の絞り込まれていない段階の患者を診ること)
2、ちまたでありふれた「主訴」、「疾患」をきっちり受け持つ経験をつむこと
3、指導医とだけでなく、多くの医師、コ・メディカルと協力して問題解決の
経験をつむこと
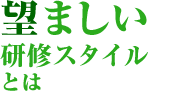
プライマリケアの経験をもつ複数の指導医による屋根瓦方式
実際にプライマリケアの視点に立ったシステマティックな研修を受けたことのある医師は今の日本には少ないのが現状です。
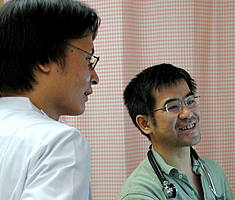
これからの臨床研修に求められるのは、実際にプライマリケアの研修を受けた経験のある若い医師の下で、しかも専門性をきわめた指導医と、新卒医師の気持ちがわかり広く最新の医学知識をもつ若手医師とが重層的に整った指導体制、すなわち「屋根瓦方式」の指導体制です。
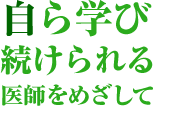
医師の研修はある意味では終わることのないものです。医学の知識・技術は、5年も経つと見直されたり新しい知見に置き換えられたりと、決して留まるものではありません。卒後臨床研修を受けることの目標は、ある一面では現時点のスタンダードな医療を身につけることにありますが、別の視点からすれば、一生自分の力で勉強し続け、常に最新でいられる力“Keeping Up to Date”の獲得であるとも言えます。そして、自分の能力や知識を本当の実力とするためには、“See one,do one,teach one”と言われるように「人に教えること」を目標にする必要があります。
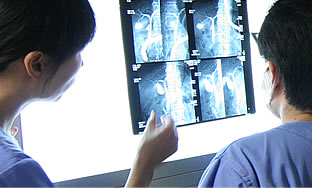
これらの能力は決して受身の研修態度では獲得できません。自分自身が研修の主人公として努力しなければなりません。
卒後臨床研修は、決して指導医やシステムの整備だけで良い医師が育つものではありません。臨床医として患者に感謝される医師になりたいという、研修医自身の初心があってこそスタートします。
熱意ある研修医の参加を期待しています。
Profile |

| 番場 誉 ばんば ほまれ |
|---|
| 長野県中野市出身 1990年信州大学卒 長野県民医連で初期研修、小児科研修の後、 神奈川県立こども医療センター、 長野県立こども病院で研修 現在、長野中央病院副院長 研修プログラム責任者 |