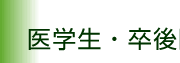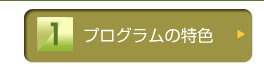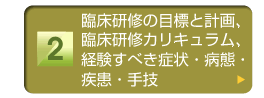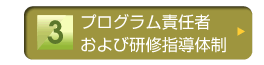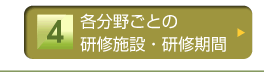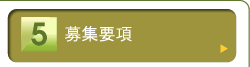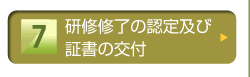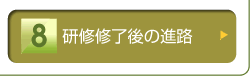|
ӮPҒDғvғҚғOғүғҖӮМ“БҗF |
|
ҒiӮPҒj—ХҸ°ҢӨҸCӮМ–Ъ“I |

|
ҒiӮQҒjғvғҚғOғүғҖӮМ“БҗF |
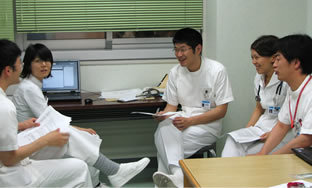
Ғ@ӮЬӮҪ’nҲжӮвҗ¶ҠҲӮМҸкӮ©ӮзҠіҺТӮр‘ЁӮҰӮйҺӢ“_ӮрҺқӮВӮұӮЖӮНҸd—vӮЕӮ ӮиҒAҲг—Гҗ¶ӢҰӮМҢ’ҚN”ЗүпӮв•ЫҢ’‘еҠwӮЦӮМҺQүБӮИӮЗ•ЫҢ’—\–hҠҲ“®ӮЦӮМҺQүБӮр•KҸCӮЖӮөӮДӮўӮйҒB ӮЬӮҪ• •”ғGғRҒ[ӮЁӮжӮСӮ`ӮbӮkӮrӮМҢӨҸCӮрҢp‘ұ“IӮЙҚsӮИӮўҒAҠо–{“IӮИҗf—Г”\—НӮЙӮЁӮҜӮйҺиӢZӮМҠl“ҫӮЙҺжӮи‘gӮсӮЕӮўӮйҒB ҢӨҸCҺw“ұ‘Мҗ§ӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAғVғjғAғҢғWғfғ“ғgҒiҢӨҸCҸI—№ҢгӮRҒ`ӮT”N–ЪҒjӮЖҺw“ұҲгӮЙӮжӮйү®ҚӘҠў•ыҺ®Ӯр“ұ“ьӮөӮДӮўӮйҒB
|
2.—ХҸ°ҢӨҸCӮМ–Ъ•WӮЖҢvүжҒAҢoҢұӮ·ӮЧӮ«ҸЗҸуҒE•a‘ФҒEҺҫҠіҒEҺиӢZ |
|
ҒiӮPҒj—ХҸ°ҢӨҸC–Ъ•WӮМӮS–{’Ң |
Ү@—ЗҚDӮИҠіҺТ-ҲгҺtҠЦҢWӮЖҲгҺtӮМҺРүп“IҺg–ҪӮрүКӮҪӮ№ӮйҲгҺtӮрӮЯӮҙӮ·
ҮAғ`Ғ[ғҖҲг—ГӮЖӮ»ӮМӮҪӮЯӮМҸЗ—б’жҺҰӮМӮЕӮ«ӮйҲгҺtӮрӮЯӮҙӮ·
ҮB–в‘и‘Оүһ”\—НӮЖҗf—ГҢvүж”\—НӮМӮ ӮйҲгҺtӮрӮЯӮҙӮ·
ҮCҲА‘SҠЗ—қӮМӮЕӮ«ӮйҲгҺtӮрӮЯӮҙӮ·
|
ҒiӮQҒj—ХҸ°ҢӨҸC–Ъ•WӮЙҠоӮГӮӯҚs“®–Ъ•W |
| Ү@—ЗҚDӮИҠіҺТ-ҲгҺtҠЦҢWӮЖҲгҺtӮМҺРүп“IҺg–ҪӮрүКӮҪӮ№ӮйҲгҺt | |
| ҠіҺТӮр‘Sҗl“IӮЙ—қүрӮөҒAҠіҺТҒEүЖ‘°ӮЖ—ЗҚDӮИҗlҠФҠЦҢWӮрҠm—§ӮөҒAӮРӮўӮДӮНҲг—ГӮМҺқӮВҺРүп“I‘Ө–КӮМҸd—vҗ«Ӯр—қүрӮөҺРүпӮЙҚvҢЈӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒA | |
| Ғi1Ғj | Ҳг—Г–КҗЪӮЙӮЁӮҜӮйғRғ~ғ…ғjғPҒ[ғVғҮғ“ӮМӮаӮВҲУӢ`Ӯр—қүрӮөҒAғRғ~ғ…ғjғPҒ[ғVғҮғ“ғXғLғӢӮрҗgӮЙӮВӮҜҒAҠіҺТӮМүрҺЯғӮғfғӢҒAҺуҗf“®Ӣ@ҒAҺу—ГҚs“®Ӯр”cҲ¬ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi2Ғj | ҠіҺТӮМ•a—рҒiүЖ‘°—рҒAҗ¶ҠҲҒAҗEӢЖ—рҒAҢn“қ“IғҢғrғ…Ғ[ӮрҠЬӮЮҒjӮМ’®ҺжӮЖӢLҳ^ӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi3Ғj | ҠіҺТҒAүЖ‘°ӮМғjҒ[ғYӮрҗg‘М“IҒAҗS—қ“IҒAҺРүп“I‘Ө–КӮ©Ӯз”cҲ¬ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi4Ғj | ҲгҺtҒAҠіҺТҒAүЖ‘°ӮӘӢӨӮЙ”[“ҫӮЕӮ«ӮйҲг—ГӮрҚsӮӨӮҪӮЯӮМғCғ“ғtғHҒ[ғҖғhғRғ“ғZғ“ғgӮӘҺАҺ{ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi5Ғj | ғCғ“ғtғHҒ[ғҖғhғRғ“ғZғ“ғgӮМӮаӮЖӮЙҒAҠіҺТҒEүЖ‘°ӮЦӮМ“KҗШӮИҺwҺҰҒEҺw“ұӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi6Ғj | Һз”йӢ`–ұӮрүКӮҪӮөҒAғvғүғCғoғVҒ[ӮЦӮМ”z—¶ӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi7Ғj | •ЫҢ’Ҳг—Г–@ӢKҒAҗ§“xӮр—қүрӮөҒA“KҗШӮЙҚs“®ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi8Ғj | Ҳг—Г•ЫҢҜҒAҢц”п•ү’SҲг—ГӮр—қүрӮө“KҗШӮЙҗf—ГӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi9Ғj | ҲгӮМ—П—қҒAҗ¶–Ҫ—П—қӮЙӮВӮўӮД—қүрӮөҒA“KҗШӮЙҚs“®ӮЕӮ«ӮйҒB |
| ҮAғ`Ғ[ғҖҲг—ГӮЖӮ»ӮМӮҪӮЯӮМҸЗ—б’жҺҰӮМӮЕӮ«ӮйҲгҺt | |
| Ҳг—Гғ`Ғ[ғҖӮМҚ\җ¬ҲхӮЖӮөӮДӮМ–рҠ„Ӯр—қүрӮөҒA•ЫҢ’ҒEҲг—ГҒE•ҹҺғӮМ•қҚLӮўҗEҺнӮ©ӮзӮИӮй‘јӮМғҒғ“ғoҒ[ӮЖӢҰ’ІӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAӮ»ӮМӢп‘М“IҺА‘HӮЖҺ©ҢИӮМ—ХҸ°”\—НҢьҸгӮЙ•sүВҢҮӮИҒAҸЗ—б’жҺҰӮЖҲУҢ©ҢрҠ·ӮрҚsӮӨӮҪӮЯӮЙҒA | |
| Ғi1Ғj | Һw“ұҲгӮвҗк–еҲгӮЙ“KҗШӮИғ^ғCғ~ғ“ғOӮЕғRғ“ғTғӢғeҒ[ғVғҮғ“ӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi2Ғj | ҸгӢүӢyӮС“Ҝ—»ҲгҺtҒA‘јӮМҲг—ГҸ]Һ–ҺТӮЖ“KҗШӮИғRғ~ғ…ғjғPҒ[ғVғҮғ“ӮӘӮЖӮкӮйҒB |
| Ғi3Ғj | “Ҝ—»ӢyӮСҢг”yӮЦӮМӢіҲз“I”z—¶ӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi4Ғj | ҠіҺТӮМ“]“ьҒA“]ҸoӮЙӮ ӮҪӮиҸо•сӮрҢрҠ·ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi5Ғj | ҠЦҢWӢ@ҠЦӮвҸ”’c‘МӮМ’S“–ҺТӮЖғRғ~ғ…ғjғPҒ[ғVғҮғ“ӮӘӮЖӮкӮйҒB |
| Ғi6Ғj | ғ`Ғ[ғҖҲг—ГӮМҺА‘HӮМ’ҶӮЕҒAҺуӮҜҺқӮҝҲгӮЖӮөӮДҸЗ—б’жҺҰӮЖ“ўҳ_ӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi7Ғj | —ХҸ°ҸЗ—бӮЙҠЦӮ·ӮйғJғ“ғtғ@ғҢғ“ғXӮвҠwҸpҸWүпӮЙҺQүБӮ·ӮйҒB |
| ҮB–в‘и‘Оүһ”\—НӮЖҗf—ГҢvүж”\—Н | |
| ҠіҺТӮМ–в‘и“_Ӯр”cҲ¬ӮөҒA–в‘и‘ОүһҢ^ӮМҺvҚlӮрҚsӮўҒA•ЫҢ’ҒEҲг—ГҒE•ҹҺғӮМҠe‘Ө–КӮЙ”z—¶ӮөӮВӮВҗf—ГҢvүжӮрҚмҗ¬ӮөҒA•]үҝӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮМҗ¶ҠUӮЙӮнӮҪӮйҺ©ҢИҠwҸKӮМҸKҠөӮрҗgӮЙӮВӮҜӮйӮҪӮЯӮЙҒA | |
| Ғi1Ғj | —ХҸ°ҸгӮМӢ^–в“_ӮрүрҢҲӮ·ӮйӮҪӮЯӮМҸо•сӮрҺыҸWӮөӮД•]үҝӮөҒA“–ҠYҠіҺТӮЦӮМ“KүһӮр”»’fӮЕӮ«ӮйҒiEBMӮМҺА‘HӮӘӮЕӮ«ӮйҒjҒB |
| Ғi2Ғj | Һ©ҢИ•]үҝӢyӮС‘жҺOҺТӮЙӮжӮй•]үҝӮрӮУӮЬӮҰӮҪ–в‘и‘Оүһ”\—НӮМүь‘PӮӘӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi3Ғj | җf—ГҢvүжӮрҚмҗ¬ӮЕӮ«ӮйҒiҠіҺТҒEүЖ‘°ӮЦӮМҗа–ҫӮрҠЬӮЮҒjҒB |
| Ғi4Ғj | җf—ГғKғCғhғүғCғ“ӮвғNғҠғjғJғӢғpғXӮр—қүрӮөҠҲ—pӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi5Ғj | “ь‘Юү@ӮМ“KүһӮр”»’fӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi6Ғj | QOLӮрҚl—¶ӮЙ“ьӮкӮҪ‘ҚҚҮ“IӮИҠЗ—қҢvүжҒiғҠғnғrғҠғeҒ[ғVғҮғ“ҒAҺРүп•ңӢAҒAҚЭ‘оҲг—ГҒAүоҢмӮрҠЬӮЮҒjӮЦҺQ“ьӮ·ӮйҒB |
| Ғi7Ғj | —ХҸ°ҢӨӢҶӮвҺЎҢұӮМҲУӢ`Ӯр—қүрӮөҒAҺ©ӮзӮМ”\—НӮМҢьҸгӮМӮҪӮЯҢӨӢҶӮвҠwүпҠҲ“®ӮЙҠЦҗSӮрҺқӮВҒB |
| Ғi8Ғj | Һ©ҢИҠЗ—қ”\—НӮрҗgӮЙӮВӮҜҒAҗ¶ҠUӮЙӮнӮҪӮиҠо–{“Iҗf—Г”\—НӮМҢьҸгӮЙ“wӮЯӮйҒB |
| ҮCҲА‘SҠЗ—қ | |
| ҠіҺТӮИӮзӮСӮЙҲг—ГҸ]Һ–ҺТӮЙӮЖӮБӮДҲА‘SӮИҲг—ГӮрҗӢҚsӮ·ӮйӮҪӮЯӮМҲА‘SҠЗ—қӮМ•ыҚфӮрҗgӮЙӮВӮҜҒAҠлӢ@ҠЗ—қӮЙҺQүжӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒA | |
| Ғi1Ғj | Ҳг—ГӮрҚsӮӨҚЫӮМҲА‘SҠm”FӮМҚlӮҰ•ыӮр—қүрӮөҒAҺАҺ{ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi2Ғj | Ҳг—ГҺ–ҢМ–hҺ~ӢyӮСҺ–ҢМҢгӮМ‘ОҸҲӮЙӮВӮўӮДҒAғ}ғjғ…ғAғӢӮИӮЗӮЙүҲӮБӮДҚs“®ӮЕӮ«ӮйҒB |
| Ғi3Ғj | ү@“аҠҙҗх‘ОҚфҒiStandard PrecautionsӮрҠЬӮЮҒjӮр—қүрӮөҒAҺАҺ{ӮЕӮ«ӮйҒB |
|
ҒiӮRҒjҢӨҸCҢvүж |
| Ғi1Ғj | ӮQ”NҠФӮМҸүҠъҢӨҸCҠъҠФ’ҶӮМҢӨҸC•ыҺ®ӮНҒAҸ«—ҲӮМҠу–]ӮЙҠЦӮнӮзӮёғҚҒ[ғeҒ[ғgӮрҠо–{ӮЖӮ·ӮйҒB |
| Ғi2Ғj | ҚЕҸүӮМ–сӮPғ•ҢҺӮрғIғҠғGғ“ғeҒ[ғVғҮғ“ӮЖӮөӮДҲК’u•tӮҜҒA‘јҗEҺнҢӨҸCӮвҠіҺТ‘МҢұҒAҲг—ГҒE•ҹҺғҺ{җЭҢӨҸCӮр’КӮөӮДҒAҲгҺtӮЖӮөӮДӮМҗSҚ\ӮҰҒAҠіҺТӮМ—§ҸкӮЙ—§ӮВҲг—ГӮМҚЭӮи•ыӮрҠwӮФҒB |
| Ғi3Ғj | ӮQғ–ҢҺ–ЪӮжӮи—ХҸ°ҢӨҸCӮрҠJҺnӮ·ӮйҒB’AӮөҒAҚЕҸүӮМӮPӮQғ–ҢҺӮНҢҙ‘ҘӮЖӮөӮДҒA“аүИӮUғ–ҢҺҒAҠOүИӮRғ–ҢҺҒAӢ~Ӣ}•”–еӮRғ–ҢҺӮрҚsӮИӮӨҒBӮ»ӮМҢгҒAҸ¬ҺҷүИҒAҺY•wҗlүИҒAҗёҗ_үИҒAғҠғnғrғҠүИҒA’nҲж•ЫҢ’Ҳг—ГӮЁӮжӮС‘I‘рҢӨҸCӮрҚsӮИӮӨҒB |
| Ғi4Ғj | Ӣ~Ӣ}Ҳг—ГӮМҢӨҸCӮЙӮВӮўӮДӮНӢ~Ӣ}•”–еӮЕӮМҢӨҸCҠъҠФӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒA“ъҸнҗf—ГӮЕӮМӢ~Ӣ}‘ОүһӮЖҒAҸҮҺҹҚsӮИӮнӮкӮйҺһҠФҠOҗf—ГҢӨҸCӮЙӮД•вӮӨҒB |
|
ҒiӮSҒj—ХҸ°ҢӨҸCғJғҠғLғ…ғүғҖ |
|
ҒiӮTҒjҢoҢұӮ·ӮЧӮ«ҸЗҸуҒE•a‘ФҒEҺҫҠіҒEҺиӢZ |
|
ӮRҒDғvғҚғOғүғҖҗУ”CҺТӮЁӮжӮСҢӨҸCҺw“ұ‘Мҗ§ |
|
ҒiӮPҒjҢӨҸCҠЗ—қҲПҲхүпӮМ”C–ұӮЖҚ\җ¬ |
| Ү@ҺеӮИ”C–ұ |
| ҢӨҸCғvғҚғOғүғҖӮЁӮжӮСҢӨҸCҲгӮМ‘S‘М“IӮИҠЗ—қҒiҢӨҸCғvғҚғOғүғҖӮМҚмҗ¬ӮЖ’Іҗ®ҒAҢӨҸCҲгӮМҸҲӢцҒEҢ’ҚNҠЗ—қ“ҷҒjҒAҢӨҸCҲгӮМҢӨҸCҸуӢөӮМ•]үҝӮЁӮжӮСҢӨҸC•]үҝӮЙҠоӮГӮӯҢӨҸCҸC—№ӮМ”F’иӮрҚsӮИӮӨҒB |
| ҮAҲПҲхүпӮМҚ\җ¬ | |||
| ҺҒҒ@–ј | ҸҠҒ@‘® | –рҒ@җE | ”хҒ@Қl |
| ҺR–{Ғ@”ҺҸә | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх’· |
| —й–ШҒ@ҸҮ | Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ | •ӣү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ҳa“cҒ@Қ_ | Ң’ҳaүп•aү@ | •ӣҲПҲх’· Ҹ¬ҺҷүИҲг’· |
ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ҢГҗмҒ@ҲА”V | ү–җKӢҰ—§•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ҠвҠФҒ@’q | җz–KӢӨ—§•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| Қb“cҒ@—І | Ҹг“cҗ¶ӢҰҗf—ГҸҠ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| җҙҗ…Ғ@җM–ҫ | ҸгҲЙ“Яҗ¶ӢҰ•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ‘qҗОҒ@ҳa–ҫ | ҢI“c•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ’r“cҒ@—ІҚD | “м’·’rҗf—ГҸҠ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ҢF’JҒ@үГ—І | ”С“c’Ҷүӣҗf—ГҸҠ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| җV“cҒ@Ҹғ•Ҫ | Ҹ¬—С”]җ_ҢoҠOүИ•aү@ | җf—Г•”’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ |
| Ҹ¬—СҒ@җMӮв | “Ң’·–м•aү@ | ү@’· | ҢӨҸCҺАҺ{җУ”CҺТ ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ”ФҸкҒ@—_ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ | •ӣү@’· Ҹ¬ҺҷүИҲг’· |
ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
| ’Ҷ“ҮҒ@•Ч | ’Ҷ“ҮҲгү@ | ү@’· | ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх ҠO•”ҲПҲх |
| җXҒ@“Д | ’·–мҺs–Ҝ•aү@ | •wҗlүИ“қҠҚүИ’· | ҢӨҸCҠЗ—қҲПҲх |
|
ҒiӮQҒjҺw“ұ‘Мҗ§ҒiҺw“ұ•ы–@ҠЬӮЮҒj |
| Ғi1Ғj | ҢӨҸCҲгҺw“ұӮЙӮНҒAғVғjғAғҢғWғfғ“ғgҒi—ХҸ°ҢӨҸCӮрҸIӮҰӮҪӮRҒ`ӮT”N–ЪӮМҲгҺtҒjӮЖҺw“ұҲгҒi•a“ҸҲг’·ғNғүғXҒjӮЖӮМ—јҺТӮӘҸd‘w“IӮЙӮ ӮҪӮйҒBҒiү®ҚӘҠў•ыҺ®Ғj |
| Ғi2Ғj | ғVғjғAғҢғWғfғ“ғgӮНҢӨҸCҲгӮМ“ъҸн“IӮИӢ^–вӮЙӮұӮҪӮҰҒAӢӨӮЙҠwҸKӮЖҗf—ГӮЙӮ ӮҪӮй–рҠ„ӮЕӮ ӮиҒAҺw“ұҲгӮНҗf’fӮЖҚЕҸI“IӮИҺЎ—Г•ыҗjӮЙҗУ”CӮрҺқӮВӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮиӮнӮҜ‘жӮP”NҺҹӮМҢӨҸCҲгӮЙӮНҒAҢҙ‘ҘӮЖӮөӮДҢӨҸCҲгӮR–јӮЙғVғjғAғҢғWғfғ“ғgӮP–јӮр”z’uӮөҒAҠe•a“ҸӮЙҺw“ұҲгӮP–јӮр”z’uӮ·ӮйҒB |
|
ҒiӮRҒjҸүҠъҢӨҸCӮМӢLҳ^ӢyӮС•]үҝ•ы–@ |
| Ғi1Ғj | ҸүҠъҢӨҸCҠJҺnӮЙӮ ӮҪӮиҒAғIғҠғGғ“ғeҒ[ғVғҮғ“ӮрҚsӮўҒuҸүҠъҢӨҸC—vҚjӢyӮСҢӨҸCҢvүжҒA•]үҝ•\Ғiғ`ғFғbғNғҠғXғgҒjҒvӮрҠeҸүҠъҢӨҸCҲгҺtӮЙ”z•zӮ·ӮйҒB |
| Ғi2Ғj | ҸүҠъҢӨҸCҲгҺtӮНҒAҠe•a“ҸҒiҠeүИҒjғҚҒ[ғeҒ[ғVғҮғ“ҸC—№ҺһӮЙ•]үҝ•\ӮЙҠоӮГӮўӮДҺ©ҢИ•]үҝӮЖҺw“ұҲг•]үҝӮрҚsӮӨҒB |
| Ғi3Ғj | ҢӨҸCҲгӮМ‘ҚҚҮ“IӮИҢӨҸC•]үҝӮНҒAӮQғ–ҢҺӮІӮЖӮЙҠJҚГӮіӮкӮй—ХҸ°ҢӨҸC•aү@ҢQӮМҚҮ“ҜҲгҺtҢӨҸCҲПҲхүпӮЙӮДҚsӮӨҒB |
|
ӮSҒDҠe•Ә–мӮІӮЖӮМҢӨҸCҺ{җЭҒEҢӨҸCҠъҠФ |
| —ХҸ°ҢӨҸCӮрҚsӮӨ•Ә–м | •aү@ҒEҺ{җЭ | ҢӨҸCҠъҠФ | |
| “аүИ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ Ң’ҳaүп•aү@ |
6ғ–ҢҺ | |
| Ӣ~Ӣ}•”–е | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ |
3ғ–ҢҺ | |
| ’nҲжҲг—Г | Ҹг“cҗ¶ӢҰҗf—ГҸҠ ҸгҲЙ“Яҗ¶ӢҰ•aү@ “м’·’rҗf—ГҸҠ ү–җKӢҰ—§•aү@ җz–KӢӨ—§•aү@ ”С“c’Ҷүӣҗf—ГҸҠ |
1ғ–ҢҺ | |
| ҠOүИ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ Ң’ҳaүп•aү@ |
3ғ–ҢҺ | |
| –ғҗҢүИ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ | 1ғ–ҢҺ | |
| Ҹ¬ҺҷүИ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ |
2ғ–ҢҺ | |
| ҺY•wҗlүИ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ ’·–мҺs–Ҝ•aү@ |
1ғ–ҢҺ | |
| җёҗ_үИ | ҢI“c•aү@ | 1ғ–ҢҺ | |
| ‘I‘рүИ–Ъ | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ Ҹј–{ӢҰ—§•aү@ Ң’ҳaүп•aү@ Ҹ¬—С”]җ_ҢoҠOүИ•aү@ ’·–мҺs–Ҝ•aү@ |
5ғ–ҢҺ | |
| ғIғҠғGғ“ғeҒ[ғVғҮғ“Ғi“аүИҒj | ’·–м’Ҷүӣ•aү@ | 1ғ–ҢҺ | |
Ҡу–]ӮЙүһӮ¶ӮД3ғ–ҢҺ’ц“xҒAӢҰ—НҢ^•aү@ҒEҺ{җЭӮЕӮМҢӨҸCӮрҚsӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒB
| ҢӨҸCғXғPғWғ…Ғ[ғӢ—б | ||||||||||||
| 4ҢҺ | 5ҢҺ | 6ҢҺ | 7ҢҺ | 8ҢҺ | 9ҢҺ | 10ҢҺ | 11ҢҺ | 12ҢҺ | 1ҢҺ | 2ҢҺ | 3ҢҺ | |
| ӮP”NҺҹ | ғIғҠ | “аүИ | “аүИ | “аүИ | “аүИ | “аүИ | “аүИ | ҠOүИ | ҠOүИ | ҠOүИ | Ӣ~Ӣ} | Ӣ~Ӣ} |
| ӮQ”NҺҹ | Ӣ~Ӣ} | ҺY•w | җёҗ_ | Ҹ¬Һҷ | Ҹ¬Һҷ | ғҠғn | ғҠғn | ’nҲж | ‘I‘р | ‘I‘р | ‘I‘р | ‘I‘р |
|
ӮTҒD•еҸW—vҚҖ |
| 1.ғvғҚғOғүғҖ–јҸМ |
’·–м’Ҷүӣ•aү@—ХҸ°ҢӨҸC•aү@ҢQҢӨҸCғvғҚғOғүғҖ |
| ғvғҚғOғүғҖ”ФҚҶ |
030354401 |
| 2.•еҸW’иҲх |
5–ј |
| 3.ҸҲӢц |
(ӮP)җg•ӘҒ@ҸнӢОҗEҲхӮЖӮөӮДҚМ—pҒAҺРүп•ЫҢҜҒAҢъҗ¶”NӢаҒAҳJҚР•ЫҢҜҒAҢЩ—p•ЫҢҜҠ®”х |
| 4.үһ•еҺ‘Ҡi |
ҲгҺtҚ‘үЖҺҺҢұҚҮҠiҺТ(Ң©ҚһӮЭҠЬӮЮ) |
| 5.үһ•е•ы–@ |
(ӮP)ҸoҠиҠъҠФҒ@2013”N7ҢҺ1“ъҒ`8ҢҺ––“ъ |
| 6.Ӯ»ӮМ‘ј |
(ӮP)‘IҚlҺҺҢұҺуҢұҠу–]ҺТӮНҒAҺ–‘OӮЙҺАҸKӮЬӮҪӮНҢ©ҠwӮрҚsӮӨӮұӮЖҒB |
|
ӮUҒDҸҲӢц |
| җg•Ә | ҸнӢОҗEҲхҒiҺРүп•ЫҢҜҒAҢъҗ¶”NӢаҒAҳJҚРҒAҢЩ—p•ЫҢҜ—LӮиҒj |
| ‘ТӢцҒi”NҠФҒj | 1”NҺҹҒ@6,536,000ү~Ғi‘O”N“xҺАҗСҒj 2”NҺҹҒ@8,297,600ү~Ғi‘O”N“xҺАҗСҒj ҸЬ—^”NӮQүсҒAҢӨӢҶҺи“–ҒA—ХҸ°Һи“–ҒA“–“ъ’јҺи“–ҒAүЖ‘°Һи“–ҒAҸZ‘оҺи“–—LӮи |
| ӢО–ұҺһҠФ | ӮWҒFӮSӮTҒ`ӮPӮVҒFӮPӮTҒiҺһҠФҠOӢО–ұ—LӮиҒj |
| ӢxүЙ | ӮSҸTӮVӢxҲИҸгҒA—LӢxӢxүЙҒAүДҠъӢxүЙҒA”N––”NҺnӢxүЙ“ҷ |
| “–’ј | ӮSүсҒ^ҢҺҒiҺw“ұҲгӮЖӮЖӮаӮЙ•Ўҗ”“–’ј‘Мҗ§Ғj |
| ҸhҺЙ | —LӮи |
| Ң’ҚNҠЗ—қ | Ң’ҚNҗf’fӮр”NӮQүсҚsӮИӮӨ |
| ҲгҺt”…ҸһҗУ”C•ЫҢҜ ӮМҲөӮў |
•aү@ӮЙӮЁӮўӮДүБ“ьӮ·Ӯй |
| ҠO•”ӮМҢӨҸCҠҲ“® | ҠwүпҒEҢӨӢҶүпӮЦӮМҺQүБӮНүВ”\ҒB’AӮөҺQүБ”пҒEҢр’К”пӮМҺxӢӢӮНҢҙ‘ҘӮЖӮөӮД”NӮQүс |
| ғAғӢғoғCғgӮМ—L–і | ӢЦҺ~ӮЖӮ·Ӯй |
ӮVҒDҢӨҸCҸC—№ӮМ”F’иӢyӮСҸШҸ‘ӮМҢр•t |
ӮWҒDҢӨҸCҸC—№ҢгӮМҗiҳH |
ҸүҠъҢӨҸCӮЙӮВӮўӮДӮМӮЁ–вӮўҚҮӮнӮ№ |
Ғ@’·–м’Ҷүӣ•aү@Ғ@ҲгӢЗҺ––ұүЫҒ@Ғ@ҲгҠwҗ¶’S“–ҒFҷB“c
Ғ@TELҒF026-234-3307Ғ@Ғ@FAXҒF026-234-3254(ҲгӢЗ)
Ғ@E-MAILҒFigakusei@healthcoop-nagano.or.jp