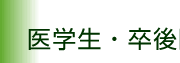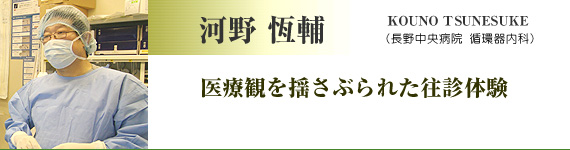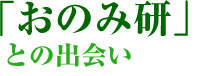
入学した年に信州大学で医学生ゼミナールが開かれることになっていて、新歓期から医ゼミ実行委員の勧誘がさかんであった。「全国の医学生と友達になれるよ」という謳い文句に誘われて、僕も実行委員になった。(当時はクラスの約半分が実行委員だった)。実行委員の中に「将来はへき地で医療をやりたい。へき地医療を考えるサークルをつくろう」という先輩がいて、僕も、「信州なら、やっぱりへき地医療もいいなあ」などという軽い気持ちで参加した。サークル名は、「お茶とのざわ菜民主医療研究会」略して「おのみ研」。
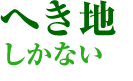
そのなかで、阿南町のへき地診療所で20数年間医療にあたってこられた金子勇医師の話は僕のその頃の医療観を大きくゆさぶるものであった。「へき地医療は昔から存在したのではない。へき地は高度経済成長の産物であって、人為的なものだ。へき地医療を解決するためには、へき地を生みだしたおおもとを解決しないといけない。」という話は、へき地とか病気とか貧困とかは、運命的なものであると何となく考えていた僕へのカウンターパンチであった。「へき地には感動的な医師がいる、自分が行くのはへき地しかない。」とまで意気込んで、診療所から帰ってきた。
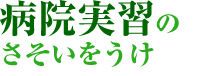
当時、実習は一週間がスタンダードで、低学年にあわせて看護体験や栄養科、外来窓口、医療生協の班会への参加など、体験を重視するものが組んであった。けっこうハードな実習の中で、まじめに医療に取り組む集団があることを実感した。とくに医局の雰囲気の明るさと、生き生きとはたらいている看護婦の姿に、いたく感動した。それでも、「なんでへき地医療をやらないんですか?」などと、少し挑発的に医師や事務職員に質問にしてみたり、「河野くん、君は将来はどうするつもりなの?」と聞かれると、「僕はへき地へ行って、診療所をやるつもりです!」などと答えていた。
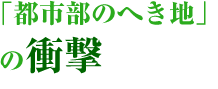
善光寺の門前町の裏通り、狭いごみごみとした路地を分け入り、どんどん家の中に入っていく往診先の光景は、僕の医療観を再びゆさぶった。当時の在宅の現場は、現在よりももっと困難な状況で、独りぽつりと、すきま風の吹き込む居間の布団で寝かされている老人や、床ずれと失禁で不潔な状態のまま寝かされている老人がいた。そんな患者を目の当たりして、なかば呆然としている僕を尻目に、明るく声を掛けながらごく自然に介護や処置をしていく看護婦、やさしく胸に聴診器をあて、手首に触れて脈をとる中野医師の姿は、僕への無言のメッセージであった。
往診も終わりになったとき、「これが都市と言われる長野市の医療の現実なんだ」という中野医師の言葉で、「都市部のへき地」という、一見矛盾している言葉の意味が、そして病いのもつ社会的側面がようやくわかったような気がした。
その後、民医連の医師や職員、学生の中での成長を通じて、僕は長野県民医連への参加を決意した。それはなによりも、衝撃的な大学一年目の夏を原点として、医療の現状を変革しうる民医連のロマンに感動したからに他ならない。
Profile |

| 河野 恆輔 こうの つねすけ |
|---|
|
福井県生まれ 1991年信州大学卒。長野中央病院にて初期研修開始。松本協立病院を経て、94年に米国ロサンゼルス Good Samaritan Hospital、98年にフランス国立レンヌ大学付属病院にて不整脈に対するcatheter-ablationの研修を行う。また箕輪町にある上伊那生協診療所にて診療所研修を経験。現在、長野中央病院循環器内科部長。 |