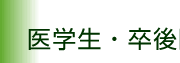心臓血管外科 後期研修プログラム |
1.はじめに |
心臓血管外科 八巻 文貴
日本に於ける心臓血管外科手術は1951年東京女子医大 榊原仟先生執刀の動脈管開存症閉鎖術によって幕をあけました。以来、年々手術技術、周辺機器の進歩により2011年には年間19万件の手術が450ほどの施設で行われています。一方、心臓血管外科医師の総数は研修医を含め2800人程度です。外科医の総数自体の不足が心配されているなかでの微増傾向ということで比較的恵まれているようにも思えます。またTVドラマでも取り上げられた、あるいは天皇陛下の手術で注目を集めた影響もあるのかもしれませんが、国民の高齢化に伴う手術総数増加に見合っただけの増加は得られていません。
心臓血管外科医を目指す医師は少ないのでしょうか。希望する上でのハードルは何でしょうか。きつい、たいへん、神経を使いそう、いずれもその通りとは思います。朝から夕方までの長時間手術。術後もICUで目が離せません。ちょっとの「ミス」と言えないような誤りが患者さんの容態に大きな影響を及ぼすこともよく経験します。ただそれは心臓血管外科に限ったことではありません。他の外科でも大なり小なり同じです。
しかし最大の障害の一つであまり語られなかったことは、「先が見えない」ことではないか、と私は思います。心臓血管外科に籍を置いて何年も経験を積んだ後に、自分で執刀医として手術ができるようになるのかわからない、という問題です。例えばたくさんの手術症例がある病院ではそれなりに経験が積めるでしょうが、術者は数名でピラミッド状にスタッフが構成されています。後期研修を終了した若者の全員が執刀医として残ることはないでしょう。また大学病院だったら、留学に出たり関連病院で働いたりしつつ、十数年に一人の教授をめざすか、関連施設のチーフの席が空くのを待つしかありません。誰が残れるのか。誰が心臓血管外科医として働き続けられるのか。その選択は実力だったり、出身大学や先輩との相性だったり、たまたまやめる人がいるタイミングだったり、その状況によって様々です。でも、考えたくもありませんが残れなかったら、席が空かなかったら…。実力不足であればあきらめもつくかもしれませんが、「運」の要素も結構ありそうです。 私もかつて皆さんと同じように不安に苛まれた一人です。
ここで我々の提案です。
現在の日本の心臓血管外科治療のレベルは高度です。少数の特別な患者さんたちをのぞいて一般病院でできない手術は少ないと思います。であるならば、高い敷居をまたいで挑戦し大学教授や TVにでるような花形外科医を目指す姿勢もすばらしいと思いますが、普通の心臓血管外科医としてきちんとした手術をおこない市井で患者さんの頼りにされる医師になる、という発想も評価されてもいいのではないでしょうか。我々はそのような目標で診療を行ってきました。
市井の外科医だからといってレベルが落ちてもいいわけではありません。むしろ大病院や大学の看板に守ってもらえないだけにしっかりした実力をもち手術結果を出さなければ患者さんや地域の医師にそっぽを向かれてしまいます。また、最近は患者さんやご家族、紹介元の内科医師もよく勉強し、可能な手術方法で病院を選ぶ方もおられます。学会などで認められた最新の治療法はきちんと身につけなければいけません。弁膜症に対する小切開手術、心拍動下冠動脈バイパス、胸部、腹部動脈瘤のステントグラフト治療、下肢静脈瘤のレーザー治療などの新しい治療法を我々も取り入れてきました。一方、補助人工心臓など施設基準上できない治療法もありますが、環境が整えば取り入れていきたいという希望は持っています。これとは反対に、革新的で、ある意味実験的かもしれない治療法は関心を持って注目しますが、我々のようなスタンスの施設が拙速に取り入れるべきではないと考えています。
我々の施設で提供できる心臓血管外科後期研修はこのような目的、意識を共有できる方を対象としています。「先が見えない」ことに対する一つの回答、我々の後継者としての後期研修の位置づけです。将来を保証するものではありませんが後継者と考えるからこそ大事に厳しく育てたいし、後期研修終了後の他施設への長期研修のプログラムも考えています。
後期研修の後に他施設で自分のキャリアを積みたい、世界に飛び出したいという希望がでてくれば、もちろんちょっと残念ですが手助けしましょう。
心臓血管外科スタッフ3名、全身麻酔手術症例120例、これ以外の末梢血管手術症例120例程度のvolumeですので十分な教育を保証するためには毎年募集することはできません。3-5年に一名程度しか公募できないと思います。
ご了解の上お問い合わせください。
日本に於ける心臓血管外科手術は1951年東京女子医大 榊原仟先生執刀の動脈管開存症閉鎖術によって幕をあけました。以来、年々手術技術、周辺機器の進歩により2011年には年間19万件の手術が450ほどの施設で行われています。一方、心臓血管外科医師の総数は研修医を含め2800人程度です。外科医の総数自体の不足が心配されているなかでの微増傾向ということで比較的恵まれているようにも思えます。またTVドラマでも取り上げられた、あるいは天皇陛下の手術で注目を集めた影響もあるのかもしれませんが、国民の高齢化に伴う手術総数増加に見合っただけの増加は得られていません。
心臓血管外科医を目指す医師は少ないのでしょうか。希望する上でのハードルは何でしょうか。きつい、たいへん、神経を使いそう、いずれもその通りとは思います。朝から夕方までの長時間手術。術後もICUで目が離せません。ちょっとの「ミス」と言えないような誤りが患者さんの容態に大きな影響を及ぼすこともよく経験します。ただそれは心臓血管外科に限ったことではありません。他の外科でも大なり小なり同じです。
しかし最大の障害の一つであまり語られなかったことは、「先が見えない」ことではないか、と私は思います。心臓血管外科に籍を置いて何年も経験を積んだ後に、自分で執刀医として手術ができるようになるのかわからない、という問題です。例えばたくさんの手術症例がある病院ではそれなりに経験が積めるでしょうが、術者は数名でピラミッド状にスタッフが構成されています。後期研修を終了した若者の全員が執刀医として残ることはないでしょう。また大学病院だったら、留学に出たり関連病院で働いたりしつつ、十数年に一人の教授をめざすか、関連施設のチーフの席が空くのを待つしかありません。誰が残れるのか。誰が心臓血管外科医として働き続けられるのか。その選択は実力だったり、出身大学や先輩との相性だったり、たまたまやめる人がいるタイミングだったり、その状況によって様々です。でも、考えたくもありませんが残れなかったら、席が空かなかったら…。実力不足であればあきらめもつくかもしれませんが、「運」の要素も結構ありそうです。 私もかつて皆さんと同じように不安に苛まれた一人です。
ここで我々の提案です。
現在の日本の心臓血管外科治療のレベルは高度です。少数の特別な患者さんたちをのぞいて一般病院でできない手術は少ないと思います。であるならば、高い敷居をまたいで挑戦し大学教授や TVにでるような花形外科医を目指す姿勢もすばらしいと思いますが、普通の心臓血管外科医としてきちんとした手術をおこない市井で患者さんの頼りにされる医師になる、という発想も評価されてもいいのではないでしょうか。我々はそのような目標で診療を行ってきました。
市井の外科医だからといってレベルが落ちてもいいわけではありません。むしろ大病院や大学の看板に守ってもらえないだけにしっかりした実力をもち手術結果を出さなければ患者さんや地域の医師にそっぽを向かれてしまいます。また、最近は患者さんやご家族、紹介元の内科医師もよく勉強し、可能な手術方法で病院を選ぶ方もおられます。学会などで認められた最新の治療法はきちんと身につけなければいけません。弁膜症に対する小切開手術、心拍動下冠動脈バイパス、胸部、腹部動脈瘤のステントグラフト治療、下肢静脈瘤のレーザー治療などの新しい治療法を我々も取り入れてきました。一方、補助人工心臓など施設基準上できない治療法もありますが、環境が整えば取り入れていきたいという希望は持っています。これとは反対に、革新的で、ある意味実験的かもしれない治療法は関心を持って注目しますが、我々のようなスタンスの施設が拙速に取り入れるべきではないと考えています。
我々の施設で提供できる心臓血管外科後期研修はこのような目的、意識を共有できる方を対象としています。「先が見えない」ことに対する一つの回答、我々の後継者としての後期研修の位置づけです。将来を保証するものではありませんが後継者と考えるからこそ大事に厳しく育てたいし、後期研修終了後の他施設への長期研修のプログラムも考えています。
後期研修の後に他施設で自分のキャリアを積みたい、世界に飛び出したいという希望がでてくれば、もちろんちょっと残念ですが手助けしましょう。
心臓血管外科スタッフ3名、全身麻酔手術症例120例、これ以外の末梢血管手術症例120例程度のvolumeですので十分な教育を保証するためには毎年募集することはできません。3-5年に一名程度しか公募できないと思います。
ご了解の上お問い合わせください。
2.研修項目 |
| 1.医の倫理に基づいた適切な態度と習慣を身につける |
| 心臓血管外科に関する十分な専門的知識と技量を有する者を養成し、社会からの信頼と評価を得て、医療の中で位置付けされるための専門医資格獲得を目的とする。 また医療技術のみならず強い責任感と倫理観を持ち、医療事故防止対策、感染対策、医療経済等にも十分に配慮できる有能かつ誠実な、信頼される心臓血管外科専門医を育成する。 |
| 2.医療安全管理セーフティマネジメントの研修を受ける |
| 医療安全管理委員会は、策定した医療安全管理指針に基づき概ね6か月に1回の医師を含めた全職員を対象に研修会を開催し、医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることで、事故を無くし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることをすすめている。 |
| 3.生涯学習を行う方略の基本を習得し実行できる |
| 急速に発展を遂げる心臓血管外科の治療方針、手技、薬剤、周辺医療機器に関する知見のアップデートは必要欠くべからざるものである。 当科では抄読会および症例検討会を週各1回、循環器科と協同開催し、循環器疾患全般の研修を行う。 定期的な学術集会、地域研究会への参加を病院として保証し学術集会での発表、研究論文および症例報告の発表を推奨する。 |
| 4.医療経済・保険について研修する |
| 保険制度全体が見直される時代の中で、高齢化社会への対応及び人口動態への対応、地域医療における病院の果たす役割・機能・連携の在り方、及び病院の経営、利用者の経済的負担と治療継続などあらゆる分野から総合的に治療を進めるために概ね年2回の研修会を開催する。 |
3.手術症例数 |
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 平均年数 |
| 121例 | 121例 | 169例 | 137.0例 |
4.カリキュラム |
【1年次】
【2年次】
【3年次】
| 教育方針 |
| 医療技術のみならず強い責任感と倫理観を持ち、医療事故防止対策、感染対策、医療経済等にも十分に配慮できる有能かつ誠実な、信頼される心臓血管外科専門医を育成する。 第一年目はこの目的の基礎形成を目指す。心臓・血管系の発生、構造と機能を理解し、心臓・血管疾患の病因、病理病態、疫学に関する十分な知識を持つ。 心臓疾患・血管疾患の診断に必要な問診および身体診察を行い、必要な基本的検査法、特殊検査法の選択と実施ならびにその結果を総合して心臓・血管疾患の診断と病態の評価ができる。 診断に基づき、個々の症例の心身両面に対応して心臓・血管疾患に対する手術方法を適切に選択し、安全に実施することができる。 関連分野の教科書、論文を熟読し、学術集会に参加し、基本知識を習得する。 |
| 方策 |
| ◆症例の種類◆ |
| 当科における心臓血管外科手術は後天性心疾患、成人先天性心疾患、大動脈疾患、頸部から下肢の末梢動脈疾患、静脈瘤、透析用シャント手術などである。これらの実地手術を通じて心臓血管外科医としての基礎部分の構築をおこなう。 心電図、心血管超音波検査、心臓血管カテーテル検査を実施し、放射線検査所見などを分析する。 心臓・血管疾患の内科治療の知識を習得する。周術期管理などに必要な病態生理の基本を理解する。周術期の輸液・輸血について 適切に施行することができる。胸部レントゲンで無気肺、気胸、肺炎、胸水貯留、心不全が診断できる。 |
| ◆症例数◆ |
| 当科で施行する手術に助手として参加する。おおむね開心術、心拍動下冠動脈バイパス術合計で60-70例、ほかのステントグラフトを含めた大動脈手術20-30例である。 またこのほかにレーザー治療を含めた静脈瘤手術が20-30例、透析用シャンを作成手術が30-40例である。 これらの手術に助手として、あるいは平易な症例では指導医のもと執刀医として研鑽を積む。 また心臓血管外科領域に重複する他科疾患についてもICUにおいて指導医のもとに協力して診療にあたる。 |
| ◆手術の範囲◆ |
| 合併症のない通常の心臓血管外科手術において、開閉胸、開閉腹などの基本的手技が問題なく施行できることを目標にする。 また体外循環(人工心肺)と心筋保護を現場で理解し、回路の組み立てやバランス計算方法など体外循環技術の基本について習得する。可能であれば体外循環設立のためのカニュレーション手技を施行する。 またこのためには手術をはじめとする外科診療上必要な局所解剖について理解していなければならない。 |
【2年次】
| 教育方針 |
| 手術室内での基本的手術手技を習得するのみならず、主体的に基本的手技を進めうることを目標とする。 このほかに診療上必要な患者さん、御家族、関連する他科医師、周囲のparamedical staffと必要なコミュニケーションを構築することができる。 患者さんとその関係の方々に病状と外科治療に関する適応・合併症・予後について十分な説明ができインフォームドコンセントを得る事ができる。 手術侵襲の大きさと手術のリスクを判断することができる。 |
| 方策 |
| ◆症例の種類◆ |
| 第一年目と同様に当科における心臓血管外科手術に助手、執刀医として従事する。 合併症のない開閉胸等の基本的手技については細かな指導医の監督がなくとも安全に施行できる。難易度(A)の心臓血管手術について指導下に執刀医となる。また術後ICUにおいては術後合併症の早期発見と迅速な対策ができることも目標となる。 さらに進んだ手技として Swan-Ganzカテーテルの挿入とそれによる循環管理、IABPの挿入とそれによる循環管理、レスピレーターによる人工呼吸管理、気管切開、心のう穿刺、胸膣ドレナージ等の処置をおこなう。 |
| ◆症例数◆ |
| 正中切開をともなう手術(60-70例)について、合併症のない症例で開閉胸を主体的に行う。また体外循環のカニュレーションについても安全に行い得ることをめざす。 難易度Aの開心術のなかではASD閉鎖手術、三尖弁形成手術(計 年2-3例)、緊急の動脈血栓摘除術を主とする末梢動脈手術(年10例)、初回症例の動静脈吻合の透析用シャント手術(20例)を執刀する。適応のある静脈瘤手術(年10例)では高位結紮+硬化療法を執刀する。また術後管理については重症例以外で主体的役割を果たす。 |
| ◆手術の範囲◆ |
| 基本的な心臓血管外科手技についてきちんとした知識、手技を身につけpit fallについて理解する。 比較的難易度の低い指導医執刀症例で第一助手として手術に参加する。 体外循環マニュアル」を実際と関連づけて理解し、基本的な成人体外循環を自身で安全に操作できる。 ICUにおいては心臓血管外科手術の呼吸・循環動態を理解し、薬剤による循環管理、呼吸器操作、酸塩基平衡、輸液、輸血、感染対策などの術前・術中・術後管理が適正にできる。 必要に応じ人工呼吸管理、IABP、PCPS挿入を考慮することができ、指導医のもと施行することができる。 |
【3年次】
| 教育方針 |
| 心臓血管外科の基本的手技を監督なしで施行しうることに加え、進んだ難易度の手術を安全に行いうることを目標とする。 また術後合併症の早期発見と迅速な対策ができる。医療事故、アクシデント、インシデント、クレームの発生に迅速かつ適切に対処できる。 活動の場を院外にもひろげ積極的に、心臓血管外科に関する研究論文および症例報告を発表する。あるいは学術集会において心臓血管外科に関する発表を演者として行う。 |
| 方策 |
| ◆症例の種類◆ |
| 同様に当科における心臓血管外科手術に助手、執刀医として従事する。 開閉胸等の基本的手技について安全に施行できる。難易度(B)の心臓血管手術について指導下に執刀医となる。 また術後ICUにおいては術後合併症の早期発見と迅速な対策を主体的に取りうることを目標となる。 必要な場合に IABP、PCPSを導入しそれによる循環管理、レスピレーターによる人工呼吸管理の処置をおこなう。 |
| ◆症例数◆ |
| 難易度(B)の心臓血管手術について指導下に執刀医となることが目標である。 合併症がなく、手技的に問題ないと判断される弁膜症手術、粘液種などの心臓腫瘍手術(年15例)について指導医のもとで執刀医となる。冠動脈バイパス術(年30例)で内胸動脈剥離を正確におこなう。冠動脈病変の適した症例では心拍動下冠動脈1枝バイパス術を執刀する。腹部大動脈手術(年30例)では、緊急以外の開腹手術では執刀医となる。ステントグラフト実施医資格取得がすんでいれば腹部ステントグラフト挿入手術を行う。適応のある静脈瘤手術(年20例)ではレーザー焼却術の執刀医となる。透析用動静脈シャントでは初回人工血管を用いたシャント手術を執刀する。 |
| ◆手術の範囲◆ |
| 難易度(B)の心臓血管手術について指導下に安全に執刀しうることを目標とする。 指導医が執刀する困難な手術時には第一助手として積極的に手術に参加する。また手術手技上のpit fallについては理解を深めた上で、適切に問題に対応し修復する、または適切に指導医の助力を仰ぐ。 心臓血管外科手術に対し臨床的判断能力と問題解決能力を修得していく基礎固めの学年と考えている。 |
5.3年間の研修後 |
3年間の当科での手術経験を生かし、さらに心臓血管外科医としての技量を高めていく。そのためには異なった手法で疾患にアプローチしていくことも自身の発展にとって必要であろう。この点からで他施設での研修は不可欠であると考えている。専門医を目指す上で心臓血管外科の中での自らのサブスペシャリティを選択し、目的に合わせた研修施設に依頼し研修を引き続き行っていく。
| 【研究施設】 現在、当院からの他施設研修先は東京女子医大心臓血管外科、国立循環器病センターなどである。このほかにも修練医の希望により、当院修練責任者を通じ他施設への修練依頼を行う用意がある。 |