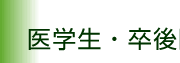腹部超音波検査 研修医 研修目標 |
1.GIOs(一般目標) |
①腹部エコー検査が有用な疾患/病態を知っていて、適切にオーダーできる。
②時間外診療において自ら腹部エコーを使用できる。
③急性の腹痛・腰痛・背部痛について自ら頻度の高い疾患のスクリーニングができる。
④入院受持ち患者において、レポートを理解でき患者に説明できる。
2.SBOs(行動目標) |
胆嚢炎と胆嚢結石の有無(胆嚢の腫大、壁の肥厚、胆泥、胆石)
胆道系の拡張の有無(総胆管の拡張、肝内胆管の拡張)
主膵管の拡張の有無
腸管の拡張と内容の停滞
尿管系の拡張所見の有無(水腎、異常な膀胱の拡張と残尿の有無)
脾臓の腫大と脾臓内出血
膵臓の腫瘤性病変
胆嚢の腫瘍性病変
腎臓の嚢胞と腫瘍性病変
腹腔内の主な脈管系の拡張
腹腔内リンパ節の腫大
生殖器系の異常
皮下の異常(リンパ節や甲状腺や乳腺など)
3.方略と課題(主に検査技師にお願いする事) |
腹部エコー機器の操作について教える(初めの数回)
Probeの選択、ゼリーの使用法、Probeの持ち方、画像の撮影の仕方、
最低限のドップラー法
腹部エコーの基本操作を教える(②の範囲でよい)
それぞれの所見の描出のための患者の姿勢・息止めの指示ができるようになる
それぞれの所見の描出のためのProbeの当て方ができるようになる
所見の標準的撮像が1ないし2方向(長軸・短軸)できるようになる
*目標とする標準画像は別紙に定める
4.研修医の心得 |
出張などで不在となることは自分で予め連絡しておく。(事務からも連絡することがあるが)
検査中に退席してよいのは、受持ち患者の急変対応か、病棟指導医から呼ばれた場合のみとする。
退席する場合は、その旨を担当検査技師に伝える事。
すべての患者を原因不明の腹痛のある患者と仮定し、最初は②の所見があるかのみスクリーニングすることに集中する。そのための基礎知識は出来るだけ教科書を読んでおくこと。
1件につき5分以内で②の所見の有無を判断し、検査技師に引きつぐ(だらだらとやらない)
②の所見が5分以内にとれるようになったら、他の課題に取り組む。
5分以内に②が判断できなければ5分の時点で検査技師に交代し、所見の撮り方を見学する。(検査技師の許可があればそれ以上でもやってよいものとするが、迅速判断に心掛ける事)
特別な所見(②でもそれ以外でも)がある患者では、検査技師の許可を受け自らProbeを操作して所見の描出に慣れることとする(見学だけでも充分とするが、「自分でその所見を描出できる」ことにもこだわり、複雑なViewやprobe操作にチャレンジする事)
職員ボランティアや相互にやりあう実習は研修医自ら依頼・セッティングしてください。
研修医の獲得すべき手技 |
Step 1(まず優先的に習熟するもの) |
| 腹水の有無(基本的に仰臥位で) | |
| 部位 | 肝右葉の周囲(横隔膜との間、右腎との間)と、右回盲部から膀胱周囲の下腹腔 |
| 課題 | 液体を疑わせるエコーフリースペースの検出 |
| 目的 | 腹腔内出血、腹水の現れる異常の否定ができるようになること |
| 胆嚢の所見(仰臥位で、必要なら状態を起こしたり側臥位で) | |
| 部位 | ①右季肋部の胆嚢長軸像の描出と撮影(できれば短軸像も) |
| 課題 | 胆嚢の腫大(長径8cm以下、短径4cm以下を正常とする) 壁の肥厚(3mm以下が正常とする) 胆石の有無、胆泥の有無 |
| 目的 | 胆嚢炎(あるいは胆嚢胆石症)を発見できるようになること |
| 腎臓の所見(左右とも、側臥位ないし伏臥位で行ってください) | |
| 部位 | 両腎の長軸像の描出と撮影 |
| 課題 | 水腎所見の有無(中心部高エコーの解離が5mm以内を正常とする) 可能であれば脈管をドップラーで確認 |
| 目的 | 尿管結石など尿管閉塞をおこす疾患の発見ができるようになること 可能であれば膀胱あたりもチャレンジし、残尿などチェックできるように! |
Step 2(その描出法を正しく知っているだけでもよいが、出来るのが望ましい) |
| 胆管の所見 | |
| 部位 | 肝門部エコーで総胆管の長軸、肝内の胆管と門脈の描出 |
| 課題 | 肝門部で下大静脈と門脈と総胆管が鑑別できること 肝内で門脈と肝内胆管が鑑別できること 胆管の直径の測定 (総胆管8mm、総肝管6mmまでが正常範囲とする) |
| 目的 | 閉塞性黄疸や心窩部痛の患者において、外科的黄疸の検出のため |
| 膵臓の所見 | |
| 部位 | 膵臓の長軸で、脾静脈や膵管の見えるところ |
| 課題 | 膵臓の短径計測(3~4cmが正常範囲) 膵管の太さの計測(見えない~2mm以下が正常範囲) |
| 目的 | 膵臓の描出一般に慣れる事が目標(時間外で必要かどうかはわからないが・・・) |