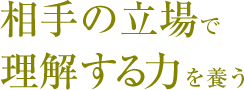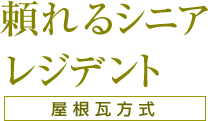期間:1年目10月〜 週1回
ローテーションしている科にかかわらず、毎週1回、継続して外来診療の研修を行っています。(昼間の一般内科外来)看護師の予診の内容で、指導医が適当と判断した患者さんの診察を行います。研修医の診察中は、隣室で指導医が診察の様子をモニターしています。検査や投薬、病状説明は、一旦指導医と相談、確認の上で行います。外来研修終了後に研修医、指導医らが集まり、振り返りディスカッションを行っています。また、年に1回、外来看護スタッフを交えて外来研修まとめのカンファレンスを開催しています。
また、SP研修(模擬患者研修)も実施しています。模擬患者役は、医療生協のSP講習会を受講した地域の組合員さんに担当して頂いています。